毎日毎日仕事は忙しい。やることも多く、時間にも追われる。
そんなときに一番しんどく感じるのが、「職場の人間関係」ではないでしょうか。
人間関係が良い状態であれば、多少大変なことがあっても「頑張ろう」と思えますし、人間関係が悪い状態であれば、仕事は順調でも「行きたくないな…」と思ってしまいます。
でも、職場の人間関係を“変える”のは難しい。相手の性格や環境をすぐに変えることはできません。
だからこそ、自分の行動や考え方を少し変えてみることで、「関係性」や「職場の空気」そのものが穏やかに変わっていくこともあると、私は実感しました。
この記事では、忙しい職場でも人間関係をラクにするために、私が実際に意識してきた7つの工夫をご紹介します。ストレスを溜め込まず、心地よく働き続けたい方の参考になれば嬉しいです。
よくある悩み:忙しい職場ほど人間関係がギスギスする理由

忙しい職場=人間関係が悪くなりやすい
と感じたことはありませんか?
私自身、繁忙期になると普段は穏やかな人がピリピリしていたり、普段通りの一言で空気が重くなったりと、“職場の空気がトゲトゲしくなる瞬間”を何度も経験してきました。
■ 時間も心も余裕がなくなる
忙しいと、まず「自分のことで精一杯」になりますよね。誰かのサポートに手が回らなかったり、ちょっとした言い回しを丁寧にできなかったり。余裕がない状態では、優しさも雑になりやすいのです。

私も、業務が立て込んでいた時に後輩から質問された際、「今それ聞く?」と内心思ってしまい、返答が急ぎ足になったり雑になったりしてしまったことがあり、後から深く反省したことがあります。
■ 伝え方が雑になる → 誤解が生まれる
急いでいると、LINEやチャットの文章も短くなりがち。「了解」「お願いします」など、シンプルすぎる言葉は、ときに“冷たい”や“怒ってる?”と誤解されやすくなることも。
私は普段から業務に関わるLINEで絵文字を使うことをあまりしないので、文章が短くなることでより冷たい印象を与えてしまうことがあります。
世間で言われている「マルハラ」にもびっくりしたのは記憶に新しいです…。

立場が変われば感じ方も違うので、「そういう感じ方もあるのか」と勉強になりました。
■ 「察してくれない」にイライラしてしまう
忙しいときほど、「言わなくてもわかってほしい」「気づいて動いてほしい」と相手に期待してしまいがちではないでしょうか?
でも実際は、相手も同じように余裕がなく、気づけていないだけのことも多いんですよね。
「なんで○○してくれないの?」というイライラが、「どうせ言っても無駄」となり、やがてコミュニケーションが減っていく…。そんな悪循環が生まれてしまうのです。
自分に余裕がある時は、「相手の情報と自分の情報は違うかもしれない、ちゃんと言葉で伝えなきゃ」と分かっているのに、忙しくなって余裕がなくなるだけで相手に求めてしまう…。
冷静に考えると「そりゃ察しては無理だよね」と分かるのに不思議ですよね。
このように、忙しさとストレスは、職場の人間関係にじわじわと影響を与えていきます。
だからこそ、自分の言動をほんの少し意識することで、「自分も相手もラクになる」働き方ができるようになるんです。
この次では、私が実際に実践している“7つの工夫”をご紹介します。
忙しい職場で人間関係を穏やかに保つ7つの工夫
忙しい職場で人間関係を穏やかに保つには、「相手を変える」のではなく、「自分ができることを少しずつ増やす」ことが大切だと思っています。
ここでは、私が日々の業務の中で意識している7つの行動をご紹介します。
1. あいさつ+一言の「余白」を作る
ただの「おはようございます」よりも、「おはようございます!今日は〇〇ですね〜」など、軽い一言を添えることで、空気が和らぎます。
忙しいとつい会話を省きがちですが、最初の数秒で職場の雰囲気が変わることって意外と多いんですよね。
女性同士の会話だと、相手のちょっとした変化(髪型・メイクなど)を話題にすることも良いと思います。

私は、そういった変化に気づきにくかったり気づいても自信がなかったりで中々言い出せないですが、相手の観察が得意な人はおすすめです。
私のように得意でない人は無理に話を広げる必要はありません。「暑いですね〜」「今日は人多そうですね」など、“天気の話”や“観察したこと”を添えるだけでも、関係性がスムーズになります。(意外と相手から話を広げてくれたりします!ありがたい!)
2. 相手の“背景”を想像する癖をつける
きつい言い方をされたとき、「何その言い方…」と反応してしまいそうになりますが、その言葉の背景には“疲れ”や“焦り”があるのかもしれません。
たとえば、「今じゃなくてもいい?」という冷たい返事も、「他のタスクに追われて余裕がないのかも」と想像できると、少し見方が変わります。
言葉はあくまで言葉として受け取る。相手の背景は想像するけど、ネガティブな方に深読みをしないのがポイントです。
感情をぶつけ合うのではなく、「この人、今日は余裕なさそうだな」と思えるだけで、自分の気持ちも落ち着きます。
3. 自分の感情を整える“5秒ルール”を持つ
イラっとしたときやカチンときたとき、すぐに反応しない習慣を持つとトラブルを防げます。私は「反応する前に5秒深呼吸」するようにしています。
その場から一旦離れたり、水を飲んだりするだけでも、感情の波は静かになります。「あとで冷静に伝える」選択肢も持てるようになりますよ。
イラっとした時にすぐに反応してしまった言葉って後悔しやすいんですよね。
あの時、あんなこと言わなければ良かった、もっとこうやって言えば良かったとなりやすいです。発してしまった言葉は無かったことにはできないので、感情のままに発することは避けたいものです。
忙しい時期ほど、自分の“感情の起伏”に巻き込まれないよう意識するのが重要です。
4. LINEやチャットに“クッション言葉”を入れる
チャット文化が定着した今だからこそ、文章の印象がそのまま人間関係に影響します。
「〇〇お願いします」だけでは冷たく感じられることもあるので、一言クッションを添えることで、印象が柔らかくなります。
たとえば:
文章ひとつで信頼感が生まれることもあるので、私は“型”として覚えておいて、必要な場面ですぐ使えるようにしています。
5. 「察してほしい」を手放し、自分から伝える
「○○してくれればいいのに」「気づいてほしい」と思っても、言わなければ伝わりません。
我慢してストレスをためるより、「実はちょっと困っていて…」「こうしてもらえると助かります」と、“事実+希望”をさらっと伝えるほうが、相手との関係性もラクになります。
周りに気遣いができたり、自然と察することができる人ほど相手にも同じことを求めてしまうので「なんで察してくれないんだろう?」とストレスに感じてしまうようです。でも、「察する」って立派な能力なので得意不得意があるんですよね。

私も以前は「察してほしい派」でしたが、伝えることに慣れてからは気持ちがずっとラクになりました。
6. 価値観の違いは“仕様”と割り切る
「どうしてこの人は○○しないの?」「私ならこうするのに」と思ってしまうと、ストレスは増えるばかり。
でも、価値観の違いは“その人の仕様”と割り切ることが大切です。
考え方の違いはあって当然。それを「正す」よりも「線引き」や「距離感の取り方」を工夫するほうが、関係が長続きします。
そもそも人を変えることはできないので、「この人はこうやって考えるんだ」くらいの受け止め方が、自分にとっても楽になれて過ごしやすくなりますよ。
私も、「すべての人とわかり合おうとしなくていい」と気づいてから、心が軽くなりました。
7. 自分の機嫌は自分で取る
忙しいと、つい自分のケアが後回しになります。だからこそ、仕事が終わったあとや休日に“ご機嫌を取り戻す習慣”を持つことが、心の健康に直結します。
私の場合は:
「自分の機嫌を誰かに委ねない」ことが、結果的に人間関係にも良い影響を与えてくれると実感しています。
小さな工夫が、職場の空気をやさしく変えていく
人間関係の悩みは尽きませんが、自分の小さな行動が、想像以上にまわりに影響を与えていることも多いと感じています。
まずは、どれかひとつでも取り入れてみることから。
無理なく、少しずつ、自分らしい“穏やかさ”を職場に広げていけたら、働く毎日が少しラクになるかもしれません。
「人を変えるより、自分の心を守る」意識が大切
とは言ってもどんな職場にも、「どうしても相性が合わない人」はいます。
声が大きい、言い方がきつい、何を考えているかわからない……そうした相手に対して、最初は「どうにかしたい」「わかってほしい」と思っていました。
でもある時、「その人を変えようとすること」自体が、無意識に自分のエネルギーをすごく消耗していたことに気づいたんです。
他人を変えるより、自分の境界線を引く
誰かの性格や言動を変えるのは、ほとんど不可能です。(自分と合わない人は尚更…)
それよりも、自分の心がこれ以上疲れないように“境界線”を引くことの方が、現実的で健全だと思うようになりました。
たとえば:
職場の人間関係は友達ではありません。あくまで仕事をする上での人間関係です。合わない人がいたって当たり前。必ずしも「仲良く」する必要はないと気づきました。
そうやって少しずつ、“無理に頑張らない自分”を許せるようになると、不思議と気持ちがラクになりました。
自分の気持ちは、自分で守ることが最強の防御
相手の言動に一喜一憂していた頃は、毎日気持ちがぐったりしていました。
でも、「自分がどう反応するか」にフォーカスを移すようになってから、職場の人間関係にも“ちょうどいい距離感”が持てるようになりました。
自分を守ることは、わがままではありません。
むしろ、自分の心を整えることで、まわりとも穏やかに付き合える余白ができるのだと実感しています。
まとめ|人間関係のストレスを軽くする第一歩は「自分から」
人間関係で疲れないようにするには、「無理していい人になる」必要はありません。
でも、ほんの少しの工夫や視点の転換で、職場の空気も、自分の気持ちも変わっていくことは確かです。
こうした行動はどれも小さなことですが、積み重ねていくと、“疲れにくい人間関係”ができていく感覚があります。
完璧を目指さなくていい。
嫌な気持ちを我慢する必要もない。
「自分ができることから、穏やかな関係をつくっていこう」と思えるだけで、日々のストレスは少しずつ軽くなります。
今日もあなたの職場に、少しでも穏やかな空気が流れますように…。
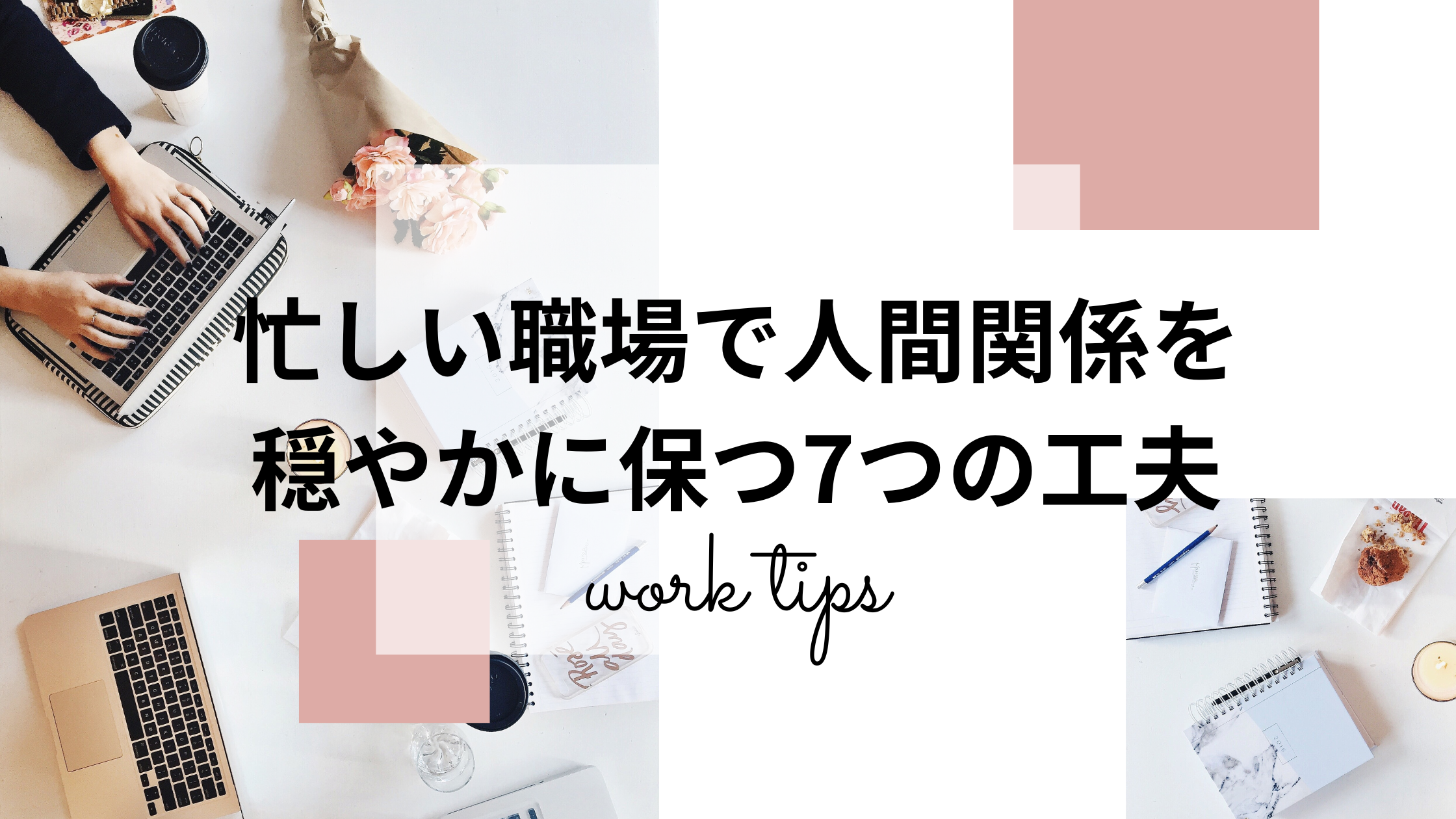
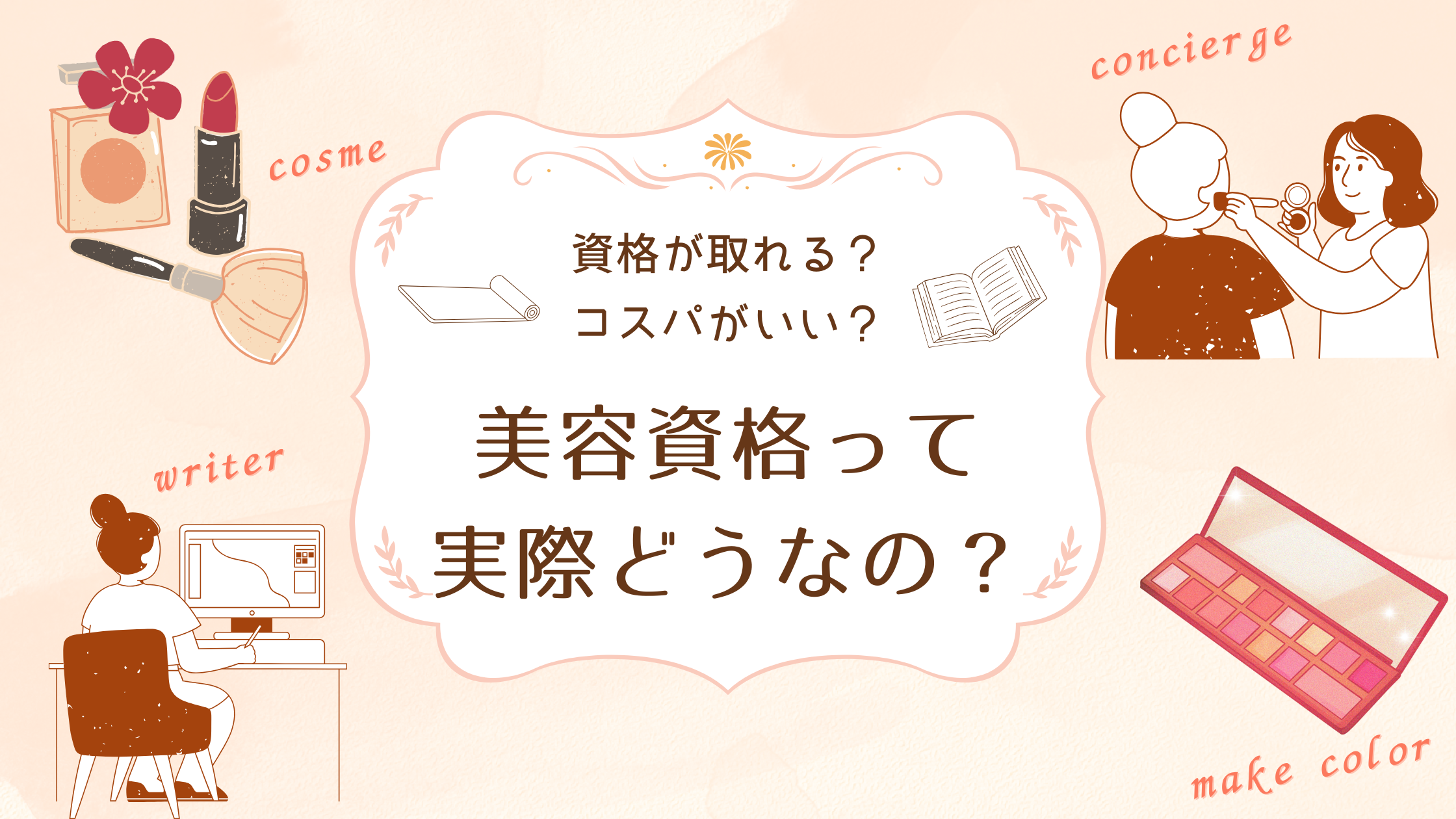

コメント